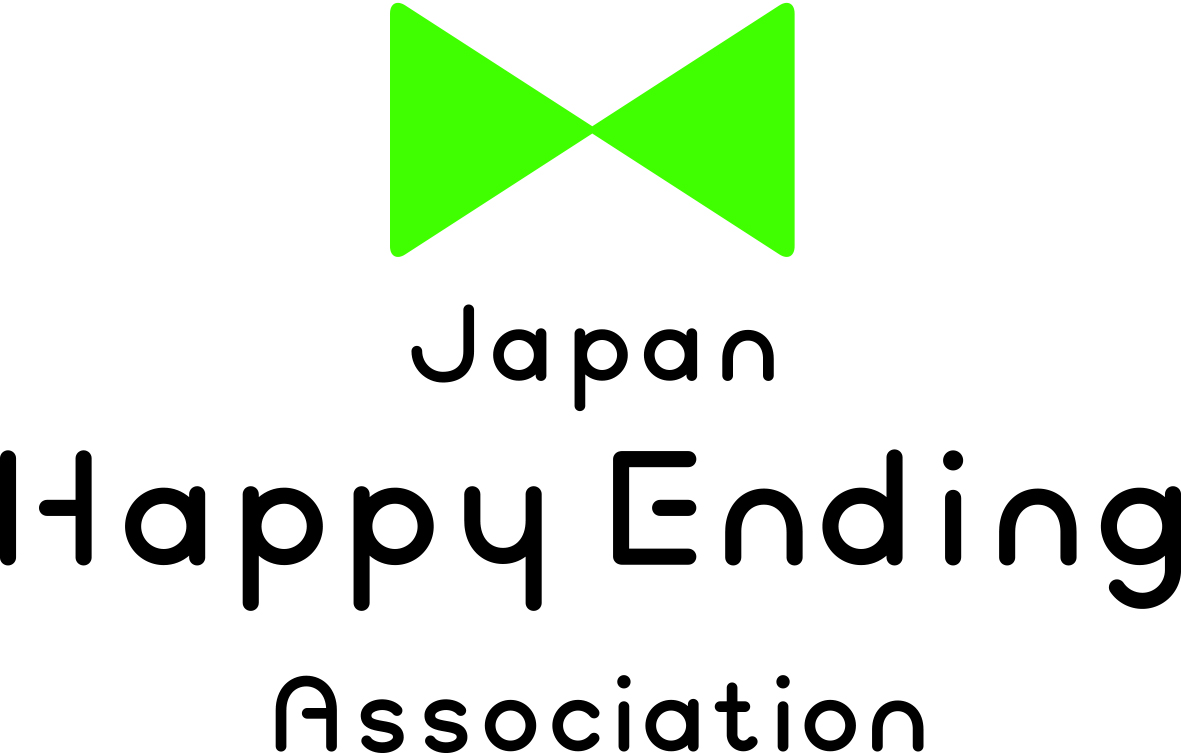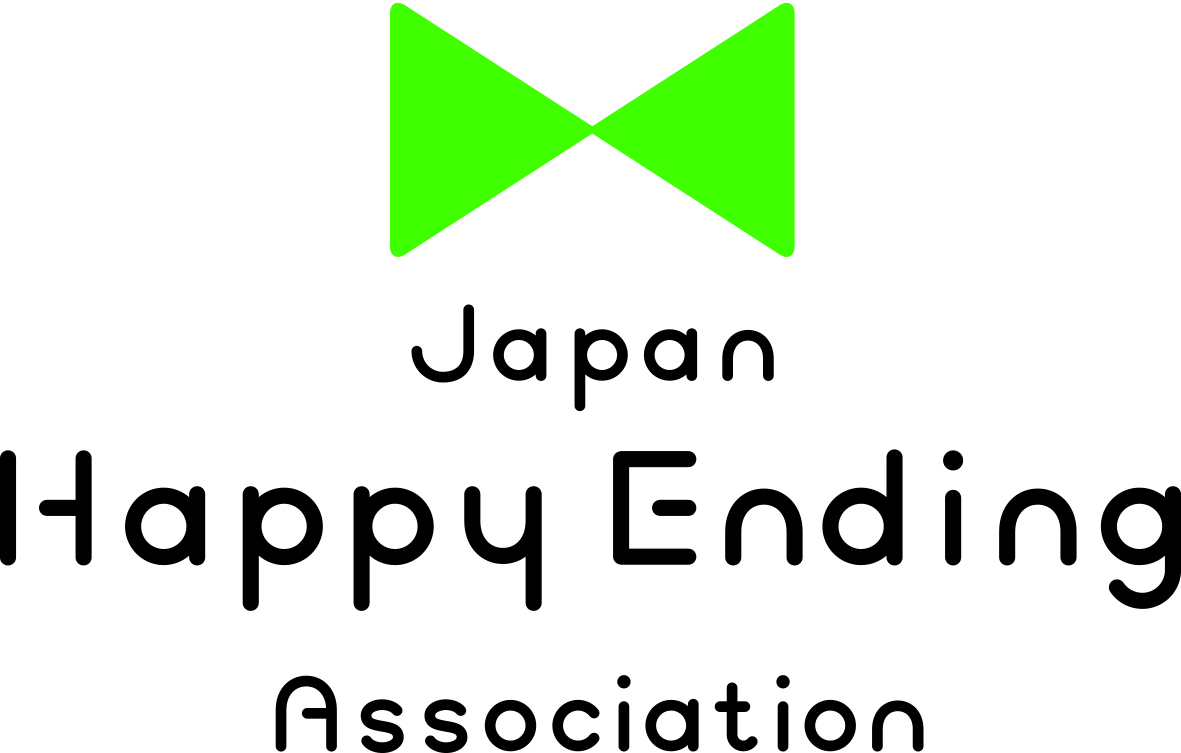墓・墓じまい・改葬


<先祖の墓が遠隔地にある>
Q. 先祖が眠る墓が遠隔地にあり、なかなか墓参りができない。また自分たち夫婦がその墓に入ってしまうと、同じように子供たちも墓参りができないので、近くに墓を移したい。
どうすれば良いだろうか?

<妻の墓を継承する人がいない>
Q. 妻の先祖の墓の継承者がいないのだが、この墓をどうすればよいだろうか?

<子ども(墓の継承者)がいない夫婦>
Q. 子供がいないために墓の継承者はいないのだが、夫婦2人で入る墓を用意したい。どのような墓がよいのだろうか?
🔹WHY? なぜ・どのような時に必要?
1. 墓が必要な理由
<1>墓は心の拠り所
墓は故人を偲ぶ場所であり、遺された家族が故人とのつながりを感じるための「心の拠り所」です。
• 家族の歴史やルーツを確認できる場:先祖や故人の存在を感じることで、自分のアイデンティティや家族の絆を再確認できます。
• グリーフケア(悲しみの癒し)の役割:家族が墓参りを通じて、故人を偲び、悲しみを整理する心理的なプロセスをサポートします。
<2>文化的・社会的な意味
• 伝統を受け継ぐ役割:墓を守ることは、家族の歴史や文化を次世代に伝えることでもあります。
• 供養の場所:日本では、故人の霊を弔い供養する場所として墓が重要な役割を果たします。
2. 無縁墓にしてしまうリスク
<1> 無縁墓の現実
• 供養がされない結果:無縁墓になると、故人を供養する人がいなくなり、墓地管理者によって撤去される場合があります。
• 遺骨の行方が不明になる可能性:撤去された遺骨は、合同墓や施設に移されることがありますが、その管理が必ずしも保証されるわけではありません。
<2>家族や親族への影響
• 心理的負担:残された家族が「供養を怠った」という罪悪感や後悔を抱くことがあります。
<3>地域社会との関係
墓が無縁化することで、墓地全体の管理が難しくなり、地域社会にも悪影響を及ぼす場合があります。墓地が荒廃することで、地域の景観や文化の価値が損なわれることもあります。
3. 改葬が必要な理由
<1>生活環境の変化に対応
• 遠方の墓が負担になる:実家が遠方にあり、墓参りが難しい場合、現在の生活圏に近い場所に移すことで供養を続けやすくなります。
• 家族構成の変化:独身者や子どもがいない夫婦など、次世代の墓守がいない場合、改葬を通じて永代供養墓や共同墓地など、負担の少ない形に移行することが可能です。
<2>墓の老朽化や管理問題への対処
• 老朽化した墓の安全性:古い墓が倒壊する危険がある場合や、管理が十分でない場合、改葬を検討することで解決できます。
• 管理費滞納の回避:管理費を支払う人がいなくなる場合、改葬して管理の負担を軽減する方法があります。
<3>供養の継続と家族の安心
改葬を行うことで、故人を引き続き供養できる環境を整えることができます。これは家族にとって心理的な安心感をもたらし、後世に「きちんと供養してくれた」と感謝される行動になります。
以上の点を念頭に墓の問題を考えてください。
🔹 HOW? どうしたらできる?
墓じまいして改葬するために必要な手続き
地方の寺にある墓を墓じまいし、近くに改葬する場合、以下の手順で手続きを進める必要があります。改葬は行政手続きや墓地管理者との調整が必要なため、スムーズに進めるためには各ステップをしっかり理解することが重要です。
1. 墓じまいと改葬の概要を理解する
・墓じまい:現在の墓地から遺骨を取り出し、その墓を撤去すること。
・改葬:遺骨を新しい墓地や納骨堂に移動すること。
これらを行うには、法律で定められた手続きを踏む必要があります。
2. 現在の墓地の管理者に相談
まずは、現在の墓がある寺院や墓地の管理者に連絡し、墓じまいと改葬をしたい旨を伝えます。
(確認すること)
<1>墓じまいの際の必要な費用(墓地使用料や永代供養料の精算など)。
<2>墓石撤去や周辺整備の条件。
<3>寺院で供養や閉眼供養(魂抜き)を行う必要があるか。
※寺院の了承がないと手続きが進められない場合もあるため、必ず相談してください。
3. 新しい墓地・納骨堂の準備
改葬先の新しい墓地や納骨堂を探し、契約を済ませます。
(確認すること)
<1>改葬先の利用条件や費用(永代供養料、管理料など)。
<2>改葬先の管理者から「受入証明書」を発行してもらう。
4. 改葬許可申請書の取得と提出
遺骨を移動するには、現在の墓地がある市区町村役場に「改葬許可申請書」を提出し、許可を得る必要があります。
(必要書類)
<1>改葬許可申請書(役所で取得)
申請書には現在の墓地管理者の署名・捺印が必要です。
<2>現在の墓地の使用許可証または証明書
<3>新しい墓地の受入証明書
申請書を市区町村役場に提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
5. 墓じまい作業
墓じまいの具体的な作業を行います。
<1>供養(閉眼供養)
現在の墓地で供養を行い、故人の魂を抜きます。寺院に依頼することが一般的です。
費用は数万円程度が目安です。
<2>墓石撤去・整地
・専門業者に依頼して墓石を撤去し、土地を整地します。
・費用は墓石の大きさや場所によりますが、数十万円程度が一般的です。
6. 新しい墓地への遺骨の納骨
改葬許可証を持参し、新しい墓地または納骨堂へ遺骨を納めます。
・新しい墓地での供養(開眼供養)や手続きは、管理者の指示に従います。
7. 寺院や関係者への挨拶と報告
墓じまいや改葬が完了したら、元の寺院や墓地管理者に報告し、挨拶を行いましょう。
<注意点とアドバイス>
<1>寺院との関係性に配慮
墓じまいはデリケートな問題なので、丁寧な説明と誠意ある対応を心がけましょう。
<2>専門業者や行政書士の活用
手続きが煩雑な場合、墓じまい業者や行政書士に依頼するとスムーズに進みます。
<3>費用の把握
墓じまいと改葬には、供養料、墓石撤去費用、改葬先の費用など、数十万円~100万円以上かかる場合があります。事前に見積もりを取ると安心です。
墓じまいと改葬は、家族の供養を継続し、遺骨を安心して管理するための重要なプロセスです。丁寧な手続きと準備を行うことで、トラブルを防ぎ、故人への供養をしっかりと続けられます。疑問点や負担がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
(ご参考)
墓じまいの作業はどのように行われるか?
🔹 HOW MUCH ? どこに相談すれば?費用はどの程度掛かるのか?
当社にご相談ください。
費用は希望される内容次第となりますので、見積もりをお出しします。
*行政への申請、墓地の管理者への交渉も一緒にお手伝いする行政書士をご紹介することができます。
*墓じまいをする墓石業者をご紹介することができます。