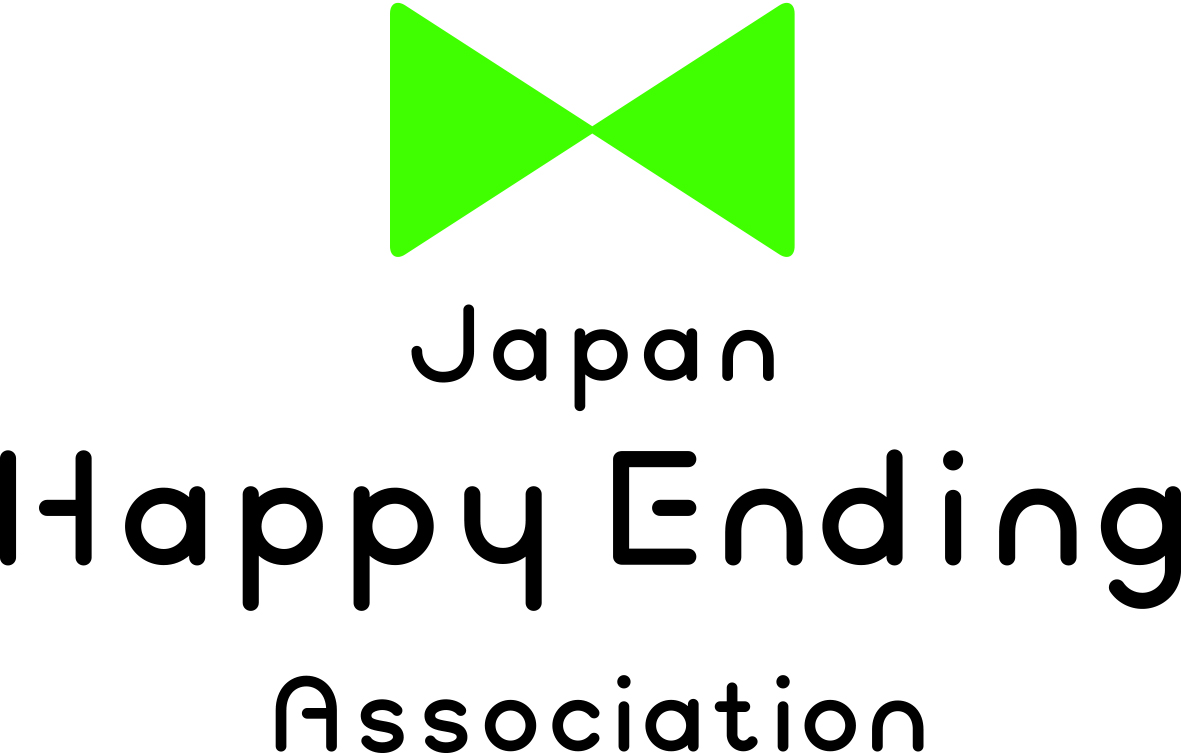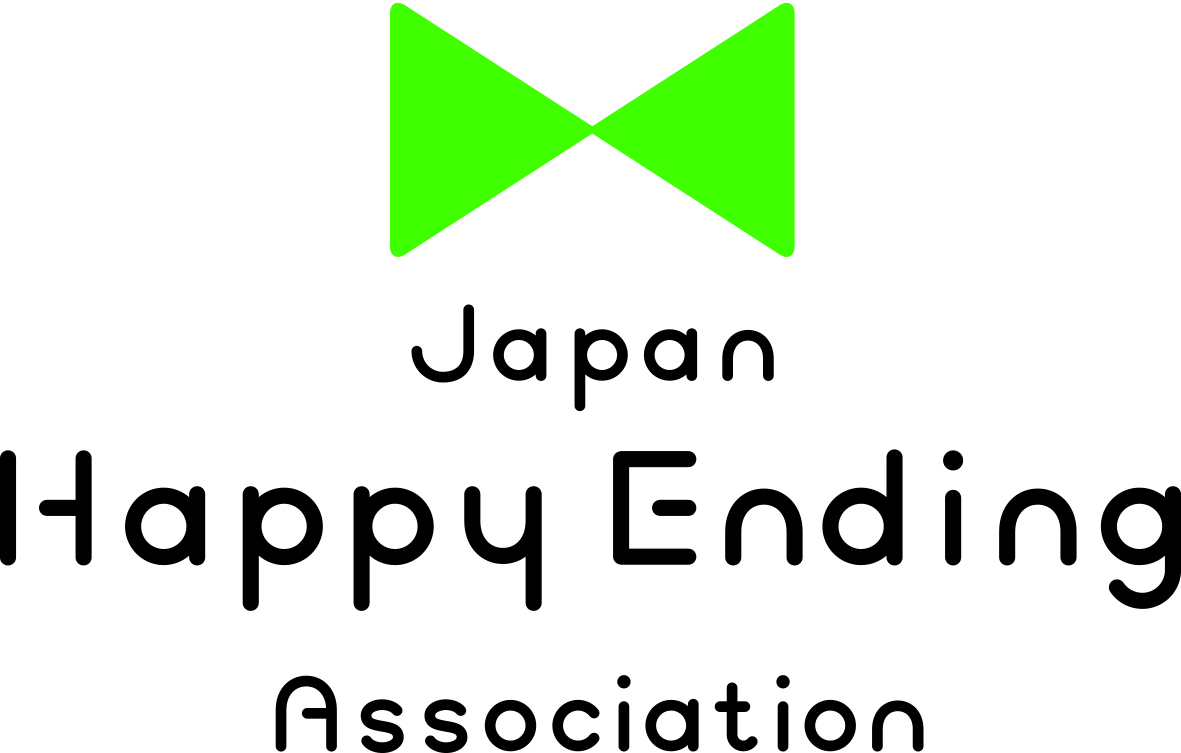相続・遺言
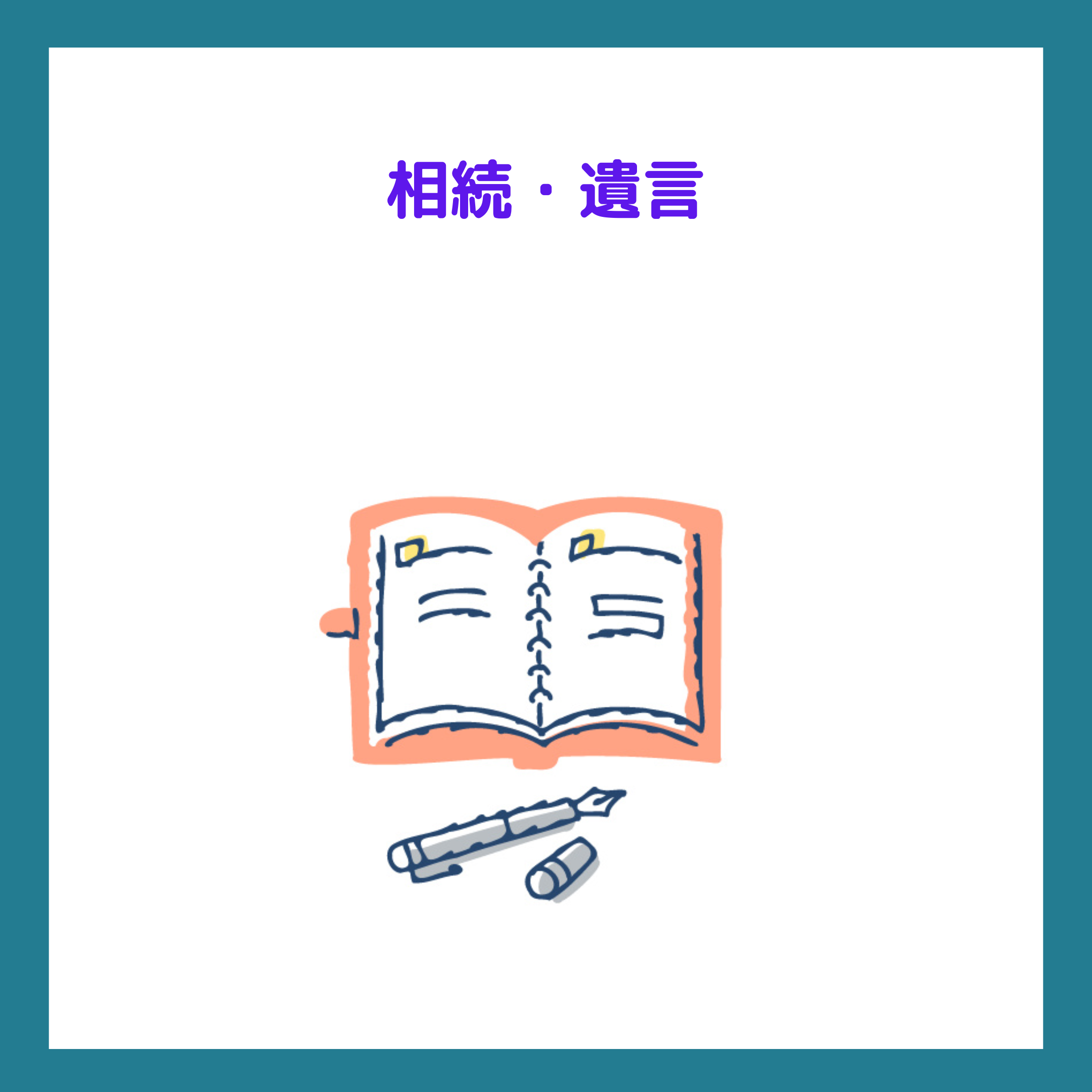

<子どものいないご夫婦の場合>
Q.私が死んだ場合には、遺言を書かなくても配偶者が全財産を相続するのだろうか?
A.被相続人(本人)に子どもがなく、兄弟がいる場合の法定相続割合は配偶者3/4、兄弟1/4です。
遺言を書くことによって配偶者にすべての財産を相続させることが可能ですが、遺言を書かなければ、1/4は兄弟に相続させる意思であったとみなされます。

<子どものいないおひとりさまの場合>
Q.子どものいない私は、老後の世話を誰かにお願いしなくてはならない。もちろん、お世話をしてくれる人にはなんらかのカタチでお礼をしなければならないと考えている。
A.子どもがいなくとも、兄弟もしくはその子(甥・姪)がいた場合にはそれらの人が法定相続人となります。
将来お世話になる人に遺産で酬いたいのであれば、遺言でその人に相続させる、あるいは遺贈する旨を書いておく必要があります。遺言は法的に間違いの少ない公正証書で作成すべきです。
さらに、お世話をしてくれる人とは任意後見契約、死後事務委任契約等も契約しておいた方がよいでしょう。
こちらのページもご覧ください。
🔹WHY? なぜ必要?
遺言を書いたほうが良い人のタイプと、その理由
遺言は、遺産相続におけるトラブルを未然に防ぎ、故人の意思を確実に反映させるための重要な手段です。特に以下のようなケースでは、遺言が不可欠となります。ご自身がそのタイプに当てはまるかどうか判定してみてください。
1. 子どもがいない夫婦<1>子どもがいない場合、法定相続では配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子ども(甥や姪)まで相続権が及びます。
☞ 配偶者にすべての財産を相続させることを希望する場合、遺言が必要です。
☞ 遠縁の親族が相続に関与し、配偶者が精神的・金銭的負担を強いられる可能性を防ぐために遺言が必要です。
2. 再婚家庭で前婚の子どもがいる場合
<1>前婚の子どもは法定相続人として必ず相続権を持ちます。再婚相手やその間の子どもと相続分を巡ってトラブルになることが多いです。
☞ 再婚相手に一定の財産を確実に残すには、遺言による指示が必要です。
3. 子どもがいないおひとりさま
<1>法定相続では親、兄弟姉妹、さらに甥や姪が相続権を持つ可能性があります。
4. 事業を営んでいる場合
家業や自営業、法人の経営をしている場合、事業承継や財産分配を明確にしないと、後継者間で争いが生じる可能性があります。
5. 配偶者や子どもとの関係が良くない場合
家族関係が疎遠または不和である場合、法定相続通りに分配すると、故人の意思とは異なる形で遺産が分配される可能性があります。
遺言は、以下の点で非常に重要です:
相続を考える上で遺言以外に一緒に考えておいた方が良いこととその理由
遺言を作成することは相続対策の重要なステップですが、それだけでは不十分な場合があります。相続に伴うトラブルや負担を減らすためには、遺言以外にもいくつかの事項を一緒に考えておく必要があります。以下に、遺言と合わせて検討すべきポイントをリストアップし、その理由を説明します。
1.財産目録の作成
遺産の種類や総額が不明確なままだと、相続人が遺産分割協議を進める際に混乱やトラブルが発生します。財産目録を作成しておけば、相続人が財産の全体像を把握しやすくなり、円滑な手続きが可能になります。
具体的な対策
<1>現金、預貯金、不動産、株式、生命保険、負債などを一覧化。
<2>定期的に財産目録を更新し、変化に対応する。
<3>負債、保証債務もマイナスの財産としてしっかり管理する。
2.生前贈与の活用
遺産が相続時に一度に渡されると、相続税が高額になる可能性があります。生前に贈与することで、相続税を軽減できる場合があります。生前贈与によって、財産の一部を事前に分配しておけば、相続時の争いを未然に防ぐことができます。
具体的な対策
<1>年間110万円の非課税枠を活用した計画的な生前贈与。
<2>特定の目的のための贈与(住宅取得資金、教育資金など)を活用。
3. 相続税対策の検討
相続税は、遺産額が基礎控除額を超える場合に課税されます。適切な対策を講じないと、相続人に大きな経済的負担を強いることになります。
特に、不動産が主な財産の場合、分割や納税資金の確保が難しくなることがあります。
具体的な対策
<1>続税評価額を下げるための生前贈与や保険商品の活用。
<2>不動産を分割しやすい形にする、または売却して現金化する。
4. 生命保険の活用
生命保険金は受取人固有の財産として扱われ、遺産分割の対象にはなりません。そのため、特定の相続人に優先的に資金を渡すことができます。
納税資金や葬儀費用の確保にも役立ちます。
具体的な対策
<1>適切な受取人を指定し、生命保険の契約内容を確認・見直す。
<2>相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用。
5. 不動産の管理・分割計画
不動産は分割が難しく、共有名義にすると管理や利用でトラブルが生じることがあります。
遺産分割や売却がスムーズに進まないと、相続人全員に負担がかかります。
具体的な対策
<1>不動産の評価額や活用方法を整理し、分割計画を立てる。
<2>売却を視野に入れる場合、事前に市場価格を調査。
6. 家族信託の検討
高齢になると認知症などで意思能力が低下し、財産管理が難しくなる場合があります。家族信託を活用すれば、信頼できる家族に財産管理を託すことができます。
遺言だけでは対応できない、長期間の資産管理が可能になります。
具体的な対策
<1>家族信託契約を結び、財産の管理や運用を信託する。
<2>信託財産の活用目的や受益者を明確にする。
7. 葬儀や埋葬の事前準備
相続の前段階として、葬儀費用や埋葬方法についての準備が必要です。遺族が故人の意思を知らないと、費用面や方法で混乱を招くことがあります。
遺言だけでなく、エンディングノートなどで希望を残しておくことが重要です。
具体的な対策
<1>葬儀の形式や費用について希望を記録しておく。
<2>埋葬場所や方法(墓地、納骨堂、散骨など)を事前に決めておく。
8. 専門家への相談と定期的な見直し
相続に関する法律や税制は頻繁に変更されるため、専門家のアドバイスが必要です。また、財産や家族状況の変化に応じて計画を見直す必要があります。
具体的な対策
<1>弁護士、税理士、司法書士、ファイナンシャルプランナーに相談。
<2>遺言や相続対策を定期的に見直し、最新の状況に対応。
遺言は相続対策の基本ですが、上記の項目も同時に考えることで、より安心でスムーズな相続を実現できます。これらの対策を計画的に進め、相続人や家族が負担を感じないようにすることが大切です。専門家の助けを借りながら、早めに準備を進めることをおすすめします。
🔹 HOW? どうしたらできる?
公正証書遺言の作成の段取り
遺言は公正証書で作成することをオススメします。
公正証書遺言のメリットは以下の通りです。
1.法的効力が強い:公証人が作成するため、無効になるリスクが低い。
2.改ざんや紛失のリスクがない:原本が公証人役場で保管される。
3.相続トラブルを防ぎやすい:法的に明確な内容であるため、相続人間の争いを最小限にできる。
以下に、公正証書遺言を作成するための具体的な段取りを説明します。
1. 作成準備
(1) 財産目録を作成する
• 遺言書の内容を決めるために、まず自身の財産を整理します。
• 預貯金、株式、不動産、生命保険、貴金属などをリストアップ。
• 負債や借入金も含めて記載。
(2) 相続人を確認する
• 法定相続人を確認し、誰にどの財産を遺贈するかを決めます。
• 戸籍謄本を取得して相続人を正確に把握。
• 特定の団体や個人に財産を遺贈する場合も検討。
(3) 要件定義:遺言の内容を具体的に決める
• 遺産の分配方法を明確にする。
• 各相続人にどの財産をどの割合で分けるのかを決定。
• 遺留分(最低限の相続権)を持つ相続人への配慮も忘れない。
(4) 証人を選ぶ
• 公正証書遺言を作成する際には、2名の証人が必要です。
• 証人の条件:
• 成年者であること。
• 相続人や受遺者、遺言執行者ではないこと。
• 公証人の親族や従業員でないこと。
(5) 必要書類を準備する
• 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
• 戸籍謄本(遺言者と相続人を証明するため)
• 不動産登記簿謄本(不動産の遺贈の場合)
• 預貯金通帳のコピー(金融資産の特定のため)
• 固定資産税評価証明書(不動産の評価額を記載)
• 証人の本人確認書類(証人が必要な場合)
2. 公証人との打ち合わせ
(1) 公証人役場を選ぶ
遺言者の住所地や財産所在地に近い公証人役場を選定します。
(2) 公証人と事前相談を行う
• 遺言の内容や必要書類について公証人に相談します。
• 作成の目的や遺産分割の希望を伝える。
• 必要に応じて弁護士や司法書士など専門家を交えて相談。
(3) 遺言の原案を作成する
• 公証人または弁護士と相談しながら、遺言内容の原案を作成。
• 公証人が法的な観点からアドバイスを行い、不備のない内容に仕上げる。
3. 公正証書遺言の作成
(1) 公証人役場での面談
• 公証人役場で、遺言者本人と証人2名が立ち会い、遺言内容を確認します。
• 遺言者が内容を公証人に口述し、公証人がそれを文書化。
• 公証人が文書を読み上げ、内容の確認を行う。
(2) 公正証書遺言の署名・押印
• 内容に問題がなければ、遺言者、証人、公証人が署名と押印を行います。
(3) 公正証書遺言の完成
• 公証人が正式な公正証書遺言を作成し、遺言者本人に交付します。
• 原本は公証人役場で保管され、紛失や改ざんのリスクがありません。
4. 遺言書完成後の手続き
(1) 遺言書の保管
• 公正証書遺言の正本を自宅や信頼できる場所で保管します。
• 遺言内容を必要な相続人や弁護士に通知しておくと安心。
(2) 必要に応じて内容を見直す
• 財産や家族構成に変更があった場合、遺言内容を更新します。
• 公正証書遺言を新たに作成する際は、以前の遺言は無効になります。
以上が一般的な公正証書遺言の作成の段取りです。
公正証書遺言作成にサポートが必要であれば当社にご依頼ください。
🔹 HOW MUCH ? どこに相談すれば?費用はどの程度掛かるのか?
公正証書遺言は公証役場で公証人が作ります。
自信がある人は公証役場に相談してください。
先述の通り、死後のことだけではなく、生前のお金の使い方を考えた上で遺言を作成するのが賢明です。
生前ならびに死後を通して財産の使い方の要件を専門家に相談したい方は当社にご相談ください。
公正証書作成以前の段階からお手伝いいたします。
必要な費用は次の通りです。
1.公証人手数料
公証人に対する公正証書作成の手数料です。
遺産の金額等によって異なりますので、ご相談ください。
2.専門家の相談料
以下を作成、コンサルティングする費用として
330,000円
<1>財産目録の作成
<2>キャッシュフロー表の作成
<3>必要な公正証書の要件定義ならびに案文作成
<4>公証役場との連絡
<5>公証役場の立会
<6.以上の全体コンサルティング